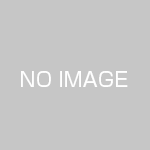就業規則で決められて一定年齢に到達したことが自由となって、雇用契約が自動的に終わることが定年制です。定年は別に決めなくとも構いませんが、決める場合、高年齢者雇用安定法第8条によって、60歳未満にすることが不可能です。
就業規則に定められている定年に対する事項は、その表現が漠然としているケースがあります。定年に到達したと認められる時点はいつになるのかは、人によって違う考え方を取ります。これに関し、「年齢計算に関わる法律」では、年齢が1つ加えられるのは誕生日の前日となっています。これを基準として定めれば、誕生日の前日を退職日と考える人もいるはずです。
退職日が含まれる月の給与の計算を複雑にしないために、就業規則などに「誕生日の前日が含まれる賃金の計算期間の賃金締切日」を定年にすることが望ましいです。賃金の締め切りが月末であれば、誕生日の当日が含まれる月の月末が定年になります。
どちらにせよ、退職日に関してはその計算を明らかにして就業規則に定めておくことがポイントです。