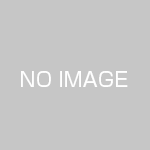会社のカギや名刺、文具類、正副、IDカード、携帯等の通信機器などのように、会社から従業員に貸しているものは、従業員が退職する時に回収することが望ましいです。返却は当然なものですが、就業規則に関連規定がないと、返却の義務がない等の主張をする可能性があります。
返却の義務があるのに返却をしない場合は、その備品に対する費用の請求が可能です。しかし、賃金には、労働法第24条による「全額払いの原則」があります。賃金は原則的に全額の支払いを行い、社会保険料や源泉徴収などの法令による控除以外は控除ができません。(労使協定などで決めた控除はできます:社宅費用、購入代金、組合費など)
このことから、「貸し出した制服の返却が無い場合、賃金から制服代として一定額を控除する」などの規定を就業規則に入れておくことが、今回のポイントとなります。
返却などの管理を省略するために、個人で使用する備品は従業員の本人が購入するようにし、その分「備品購入手当」などの形で賃金に上乗せする方法もいいでしょう。
しかし、願客データの入っているパソコンやIDカード、会社のカギなどは回収が必須となります。これらに関する返却義務にかんしては、就業規則などにきちんと規定を入れることが重要です。
*労働基準法第24条から定められている「賃金支払の5原則」
≪1≫通貨払いの原則:給与は、現金でしはらうこと。小切手や外貨通過は認定されません。労働協約の締結により、通勤定期券・現金給付の支払いなどができます。
なお、本人の同意のもとで、本人名義の銀行の口座に振り込んで支払うことも可能です。
≪2≫直接払いの原則:賃金は、従業員の本人に直接しはらうこと。しかし、「使者」としてもらう人に渡すことは認められます。
≪3≫全額支払いの原則:各期間分の全額を支払うこと。しかし、下記のケースではこの原則が適用されません。
1.法令に別段の規定があるケース―社会保険料、源泉徴収などの控除
2.労使協定を結んでいるケース―組合費、購入代金、社宅の費用など
≪4≫毎月一回以上支払の原則:毎月1回以上支払うこと。しかし、賞与や退職手当などの臨時に支払われる賃金はこの原則から除かれます。
≪5≫一定期間支払の原則:支払日を決めて支払うこと。「毎月末日」や「毎月10日」はOKですが、「毎月第4月曜日」などのように、月によって支払日が一定にならない表現は認められません。