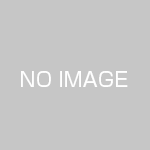多くの場合、就業規則の中に「勤務成績や勤務追行能力・技能が不良であると考えられる時」などの定めを入れますが、この規定を有効にするためには、解雇に至るまで業務に必要な能力とその能力の中から足りていないことを詳しく指摘し、改善に向けた教育訓練や指導を行うことが前提となります。
このような事実を証明するためには、対象の従業員が客観的に「能力不足」であると判断することができるようにすることがポイントです。
このことから、目標が具体的な数値で記載されている労働契約をし、他の業務や職種に配置換えを行う契約上の義務がない場合に、その目標に満たしていないという資料などを備えておくことが必要となります。これによって過去の判例から判断され、解雇が可能となる可能性が高くなります。
裁判例(1999年10月15日 東京):大学院卒の正社員としてS社に採用された従業員Aは、海外の外注管理が可能な程の英語の能力を持っていなかったこと、このことで取引先からの苦情が殺到し、外注管理の業務から排除されたこと、そして従業員の中で下位10パーセント未満の考課順位になっていたことなどから「労働の能率が劣っていて、向上も期待できない」として解雇された。
裁判では、この人事の考課が相対評価であり、平均の水準に達していないとはいえども、直ぐに「労働能率が大幅に劣っていて、向上も期待できない」とまでいうことは不可能で、また体系的な指導や教育を行って、労働の能率の向上が図れる余地があるという理由から、解雇は無効であると判断した。